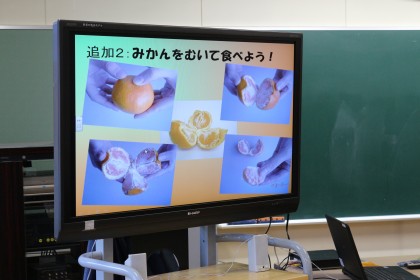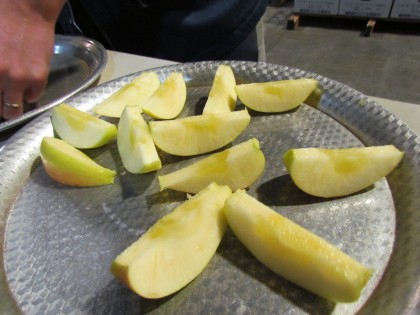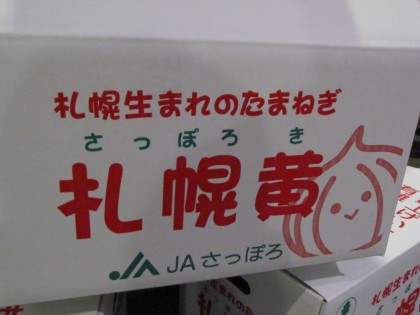JA函館市亀田からダイコンが本格入荷しています
金曜日, 12月 6th, 2013早朝、「少し暖かく感じるね!」との、あいさつが交わされていた今日(平成25年12月6日)の青果の競り場。
競りが始まる頃には、場内の気温も10度を超え、この時季にしては、ちょっぴりお仕事がしやすかったようです。
そんな中、寒くなるこれからが本番を迎える「越冬ダイコン」が入荷しています。
このダイコン、JA函館市亀田の特産の一つで、秋に一度掘り起こしたものを、再度土の中に埋めるのだそう。
そうすることで、うまみを増し、長期保存が可能となることから、年明けの2月頃まで競り場に顔を見せてくれるのだとか。
それは、これから降ってくる天からの白い贈り物が、土を覆うことで、土の中は自然の適度な冷蔵庫となり、糖分を増すのだそう。
これからの出荷の際は、もちろん雪の下から掘り起こすことから「雪の下ダイコン」とも呼ばれているそうです。
甘みの強いこのダイコン。この時季「おでんが一番だよ!」とは、小売業者さん。
「いやダイコンおろしだよ!」とは、仲卸業者さん。
「どれでもうまいよ!」と、最後に卸売業者さん。そんなことで笑顔が見られた朝でした。