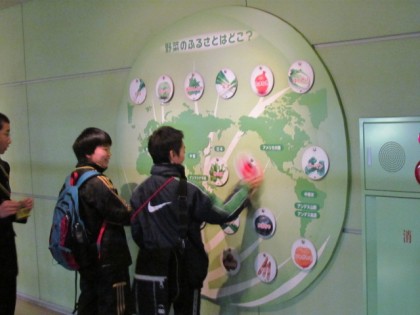ウオーキング仲間の皆さんが見学に来ました(12月7日)
木曜日, 12月 8th, 201112月7日の水曜日、札幌市東区の元町会館を拠点に、ウオーキングで健康づくりに取り組んでいる「水曜会」の皆さん、19名が市場に足を運んでくれました。
「水曜会」は、名前のとおり毎週水曜日に仲間たちが集まり、近くのパープルロード(約4キロ)を一年通して歩き続けているのだそうです。
昨年5月に、2本のポールを使った「ノルディックウオーキング」を8人で始めたそうですが、今では20人ほどが参加する会となり、時には皆さんで様々な施設へ見学にも行っているとのことです。
代表の男性は、「仲間たちと、食の安全について話す機会も増えました。そんなこともあって市場に来たのですが、特に女性の皆さんから行ってみたいと希望があったんですよ。」と、話してくれました。
「市場に隣接する環状通は、昔は川だったんですよ。」 「そう!そう!」なんて声も〜
年表を見ながら、皆さん当時のことを思い出していらっしゃいましたよ。
「水曜会」に参加をして1年ほどになりますと教えてくれた女性は、「初めて市場に来ましたが、安全・安心な食の提供のため朝早くから頑張っているのを知ることができました。」と、笑顔で話してくれました。
「ウオーキングを続けて足腰も丈夫になりました。」と、皆さん話されるだけあって、見学の際の広い施設の移動も難なくされていた姿が印象的でした。
これからもウオーキングで、仲間たちとの絆を深めてくださいね!