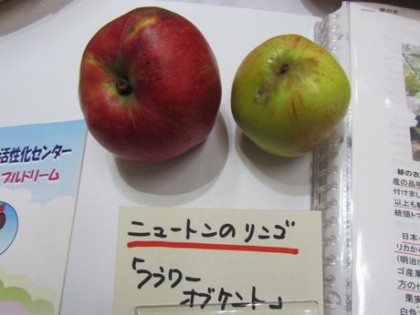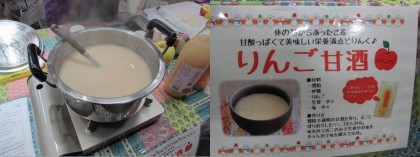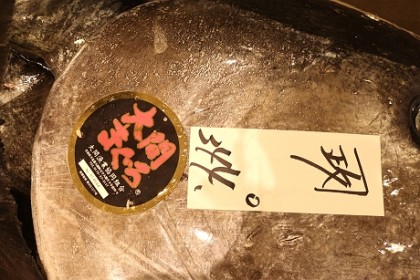お正月に向けて、八つ頭など入荷中!
月曜日, 12月 22nd, 2014当市場でも、年末年始に向けて、おせち料理用の食材が入ってくるようになりました。
まずはインパクト抜群な八つ頭です!
八つ頭は、親芋1つに複数の子芋がくっついて、それが八つの頭に見えることから、八つ頭と呼ばれているとのこと。
また、親芋が大きいことにちなんで「頭(かしら)になる」、さらに漢字の八に「末広がり」という意味もあり、縁起物としておせち料理などに使われます。
卸売業者さんによると、値段は店頭価格で1㎏あたり1,000円と少し高級な食材とのこと。
煮物にして食べるほか、本州では鍋に入れることもあるようです。
普通のスーパーなどではなかなか手に入らないようですが、ぜひいつか八つ頭の煮物を食べてみたいものです。
里芋は、山地に自生していた山芋に対し、里で栽培されることから里芋という名がついたようです。
里芋は親芋から子芋、子芋から孫芋も育ち、食用にするのは子芋と孫芋が多いようです。
ちなみに、八つ頭は里芋の一種で、親芋と子芋が分かれないため、あのような形になるとのこと。
蛇足ですが、私はおばあちゃんが作ってくれた里芋の煮物が大好物でした。
最近スーパーで買ってきたうま煮は里芋が小さくて、ごぼうとれんこんだけ食べているようで味気ないです(涙)
次はユリ根です。茶わん蒸しに入っていて、食感がシャクッて感じのものです。。。わかりずらい説明ですいません。
卸売業者さんによると、ちょっとバラして、茹でて食べてもおいしいよとか、同僚の奥様の実家では、うま煮に入っていたことがあったとのこと。
全国の生産量のうち、北海道が約98%を占めていますが、そのほとんどは京料理で多く使用される関西方面に行ってしまうとのこと。
当市場には一年の入荷量の約4分の3が12月に集中しています。
ここからは、おせち料理には関係ありませんが、私の独断でキラリと光る野菜を紹介します。
ヤーコン。。。あまりに知識がないので、当市場のブログでもおなじみ?の水産担当(ち)さんに聞いてみると、「健康にいいやつじゃなかったっけ?僕は健康よりも味優先だけどね!」と(ち)さんらしいコメント。。。
ヤーコン100gのうち、83.1gが水分、13.3gが糖質で、その糖質のうち8gが「フラクトオリゴ糖」です。
そして、このフラクトオリゴ糖こそがミソで、カロリーは砂糖の約半分で、さらに腸内ビフィズス菌の栄養源になるとのこと。
ダイエット効果もあり、健康にもいいという何ともステキな野菜です。
次は木の実?種?に分類されるようで、野菜の特集にそぐわないかもしれないのですが、クルミです。
クルミは、何と紀元前7,000年前から食糧として存在し、日本では縄文時代からオニグルミが食用とされていたとのこと。
ちなみに、上の写真がヒメグルミ(姫胡桃)、下の写真がカシグルミ(菓子胡桃)です。
仲卸業者さんによると、ヒメグルミは店頭価格で1㎏あたり1,000円以上もするのですが、これをペットの餌として購入するセレブな方もいるとか。
食用のクルミとしては、他にオニグルミ(鬼胡桃)という種類もあるらしいのですが、この殻は非常に固く、スタッドレスタイヤの材質にもなるほど。
そのような殻を普通のくるみ割りで割ることは難しいため、秘密兵器があるのです。
その名も”オニグルミ割”。。。そのままですね(笑)
さて、こういう特集をしているとお正月気分になってきます。
しかし、今年ももうあとわずか! できることはなるべく今年中に片付けて、おいしくおせち料理を食べたいものです。
皆さんもお正月にはぜひご賞味ください!