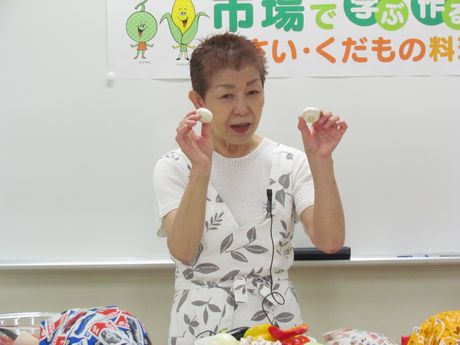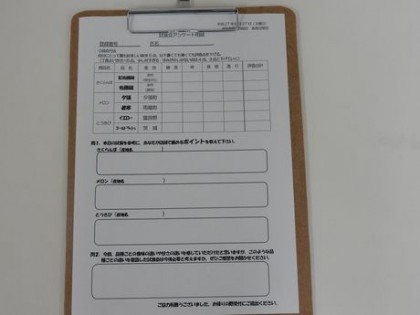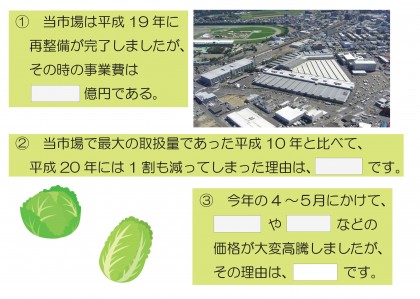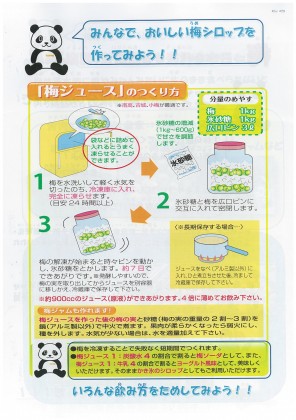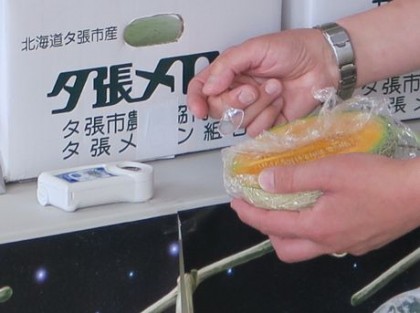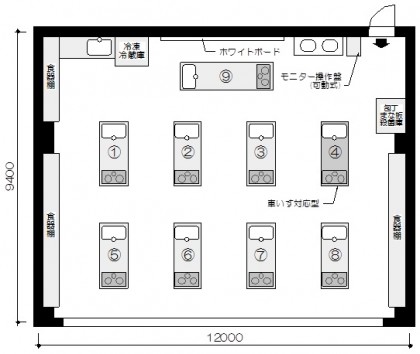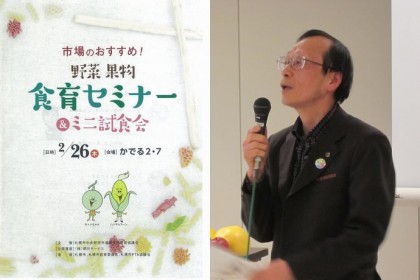市場で学ぶ・作る・食べるやさい・くだもの料理教室開催! 第3弾も親子料理教室!!!
月曜日, 7月 27th, 20157月11日(土)、青果部運営協議会主催の第3回「やさい・くだもの料理教室」「親子料理教室」が開催されました。
この料理教室は、生活習慣病の予防に効果的とされる野菜や果物を、普段の食生活に取り入れていただくことを目的として開催されています。
今回の講師は料理研究家の「東海林明子」先生です。
先生に今日の料理教室のテーマを聞いたところ、お子さん達に包丁でのいろいろな切り方を覚えてほしいとのことでした。
では、料理のほうを見ていきましょう! こちらがレシピ①、②です。
左上から時計まわりに、「チンゲン菜とコーンスープ」、「フルーツドロップマフィン」、「野菜たっぷり煮込みハンバーグ」、「キャベツたっぷりポテトサラダ」です。
今回は「キャベツたっぷりポテトサラダ」と「野菜たっぷり煮込みハンバーグ」をご紹介します。
まずは、「キャベツたっぷりポテトサラダ」です。
写真左・・・じゃがいもの皮をむく時は、先生が持っているピーラーを使いましょう!先生が左手で触っているデコボコのところでじゃがいもの根を取ります。
写真右・・・じゃがいもは皮をむいて、空気に触れると色が悪くなるので、すぐに水を張ったボールに入れてしまいます。
さて、次にじゃがいもを煮るのですが、きちんと煮えたかどうかは、つまようじがしっかり刺さればOKです。
いったんザルに移して、水を取り除きます。
写真右・・・それからもう一度鍋で煮ると、水分が飛んで「こふきいも」の状態になります。
写真左・・・熱いうちにサラダ油、酢、塩、コショウを混ぜましょう!
これで下味がしっかりつきますよ!
あとは、千切りにしたキャベツを加えると完成です!
次はメインディッシュの「野菜たっぷり煮込みハンバーグ」です。
最初はボウルにひき肉を入れ、塩、コショウ、ナツメグを加えて、よく練ります。
それから玉ねぎのみじん切りです。
半分はみじん切りで、残りは後で角切りにします。
写真左・・・玉ねぎの芯の部分を残して、縦に切れ目を入れるとこうなります。
写真右・・・そうすると、こんな風にキレイにみじん切りになりますね!
玉ねぎを切る時の包丁を支える手は「ネコの手」ですよ!
この後、玉ねぎはフライパンで炒めて、パン粉、牛乳と卵を一緒にひき肉の中に入れ、良く練ります。
次にパプリカ、ズッキーニ、マッシュルーム、玉ねぎ、なすを角切りです。
マッシュルームは十文字に切ります。
写真左・・・玉ねぎの角切りの時は、まず根を三角に切って取り、輪切りにします。
写真右・・・外側と中側の厚さが違うので、二つに分けて切ると、同じ大きさに切ることができますね!
切り終わりましたら、先ほど玉ねぎを炒めたフライパンを洗わないまま、そこにバターを入れます。
写真左・・・角切りにした野菜を炒めますが、まずは玉ねぎから炒めます。
写真右・・・すべて炒め終ったら、いったん皿へ。またまた洗わないで、このままハンバーグも焼いてしまいます!
これぞ「東海林先生マジック」!?
写真左・・・ハンバーグを手でこねますが、手に少し油をつけておくと、こねやすいです。
また、手で叩くようにして、中に空気を入れましょう。
その後は、丸いハンバーグの形にしていきます。
ハンバーグを焼く時は、後で煮込むのも考慮し、強火で表面を焼き、中は少し生なくらいで。
表面を焼くことで、形を崩さない、うま味を逃さないという効果があります。
写真右・・・ハンバーグの横に余分な油などが溜まります。
これは調味料を入れる時に邪魔なので、ペーパータオルでふき取ってしまいます。
後は調味料を加えて、先ほど角切りにした野菜も入れて、煮込むと完成です!
さあ、皆さんも作ってみましょう!
皆さん、上手くできたようですね!
ハンバーグは肉汁がたっぷりと出て、本当にジューシーな仕上がり!
ポテトサラダもお酒の肴になりそうな、いい具合のお味でした!
東海林先生、とてもおいしい料理ありがとうございました。
生徒の皆さんもお疲れ様でした。