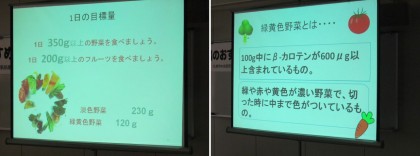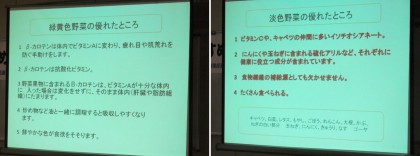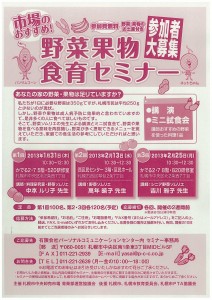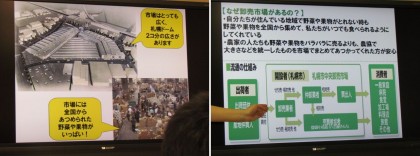11月22日、「JAありだ」の皆さんが「みかんの授業」を札幌市立藻岩北小学校で行いました。
この授業は有田みかんの良さや和歌山の農業、ひいては日本の農業に対する理解を深めてもらうことを目的として実施しているものです。
教室入ると、歓迎の飾り付けとCMでおなじみの「1日2個で♪ニッコニコ♪♫」と、テーマソングが流れ・・・
2日前まで和歌山県に植えられていたみかんの木の鉢植えと、収穫されたおいしそうなみかんが並んでいました。

「毎年、首都圏の小学生4・5年生を対象に行われている出前授業ですが、北海道で開催されるのは初めてです」と、和歌山県農業協同組合連合会北海道事務所の樫山さん。
「卸売業者さんや仲卸業者さん、学校関係者の皆さんの協力を得て、実現できました」と、笑顔で話してくれました。
当市場仲卸業者の(株)蔵重商店の蔵重さんと渡会さんも参加して、以前にメロンの授業も行なった5年生1・2組で行われました。
さあ、いよいよ授業の始まりです。
小学生記者のみんなは、事前に有田みかんについて学習し資料を作っていました。
腕にはいつものように新聞社の腕章が。

校長先生に紹介された今回の先生は・・・
みかん色のジャンパーが良く似合うJAありだの南さんです。

南さんは冗談を交えながらのおもしろいお話に子供たちはくぎづけ。
ビデオで分かりやすくみかんのことを教えてくれました。
南さん:「皆さん目を閉じてくださ~い」
「学校にバスが来ました!!千歳空港に向かいます」
「千歳空港から飛行機に乗って~関西空港まで行きました」
「それからまたバスに乗って約1時間で有田に着きました!!」
「はい、目をあけて!!」と、和歌山県の風景からビデオがスタートしました。
ナイスな演出です!!
ところで皆さん、このキャラクターをご存知ですか?

ありだみかんをイメージして生まれた「ミカピー」っていいます。
ビデオではミカピーが登場し有田を探検しながら、みかんが大切に育てられ私たちに届くまでを紹介してくれ、南さんも有田みかんの歴史や生産・収穫などの苦労話など、いろいろ教えてくれました。
いくつかご紹介しますと・・・。
有田のみかんは江戸時代の少し前に熊本県から移植され、今では全国に出荷されるみかんの10個に1個は有田みかんになるまで、増えたそうです。
一番大変な作業は、摘果(てきか)という作業で、真夏の30度以上もある中、おいしいみかんだけを枝に残す、選別作業をしているのだそうです。
そして一番気になる・・・
「おいしいみかんの見分け方」も教えてもらいましたので、皆さんに大公開しちゃいます!!
それは・・・
下の写真をよーく見てくださいよ~
みかんの表面を!

よーく見て~
左のみかんの方が“てんてん”が多いでしょ!!
南さんのお話では、てんてんが多いのは早く木に着いた実だそうで・・・
細胞分裂が盛んに行われ・・・
???・・難しい・・・。
簡単にいうと、てんてんの多いみかんは、木の上で早く生まれて、長く木の上で甘味をためているからおいしいのだそうです!!
他にも色が濃いもの、ヘタの色が黄色いものなどにおいしいみかんが多いそうです。
でも色の濃いものは見てわかりますが、てんてんの数は数えられませんよねぇ。
ご心配なく。
有田みかんは、糖度を測るセンサーを使って甘いみかんだけを出荷しているそうです。
南さん:「てんてんを数える必要はございません。有田みかんを見つければ良いのです!!」と、話がまとまったところで・・・
いよいよみかんの収穫を体験!!
実際に収穫させてもらいました。

北海道ではなかなできない貴重な体験です。
みんなは大喜び!!
そして摘み取ったみかんの甘さを、糖度計を使って測って見ました。

このみかん、小さいけど糖度は12.5度もありました。
南さん:「小さいみかんの方が甘いんですよ~」
なかには17度あるものもあったそうです。
最後に、秘技「ありだむき」を伝授してもらいました。

爪で皮をむくのではなく、へたの反対側から2つに割り、そしてさらに二つに分ける感じです。
「爪を使わずキレイにむけますので、女性にお勧めです」と、南さん。
授業の終わりに記者のみんなからたくさんの質問がありました。
質問は学校の新聞記事にまとめられ、発刊されることでしょう!!
最後に担任の佐藤先生は、授業の初めに「ありだみかんの歌」をサビの部分しか歌えなかった樫山さんへ
宿題を!
「来年までにはテーマソングを覚えて歌ってください」と、願いを込めて・・・

歌を覚えることを約束する樫山さん(左) 人ごとのように笑う南さん(右)
樫山さんはミカピーになって、「今度会うときまでに歌を覚えてきます」と、苦笑いで約束(^^♪。
照れる樫山さんを見て笑う南さん(#^.^#)。
ところが・・・
南さんも歌を覚えていなかったので・・・

約束どおりホームページに使わせていただきました(#^.^#)
こうなりました。
最後は(株)蔵重商店のお二人と、みんなも一緒にミカピーになりました。

♪1日2個でニッコニコ~♪♪
楽しい授業も終わりを迎えました。
tanu。