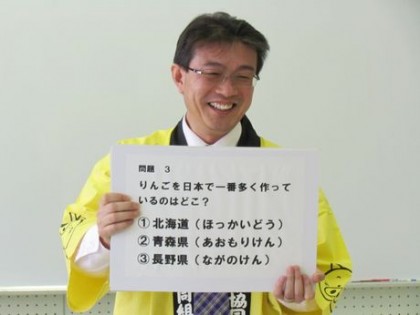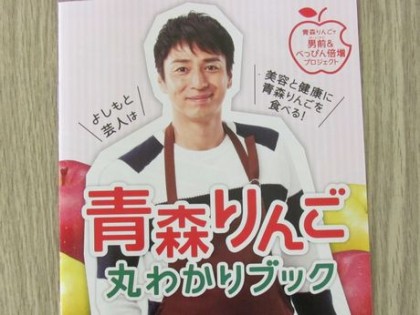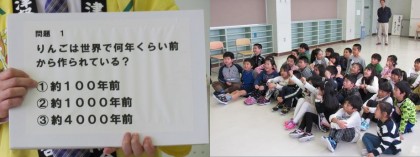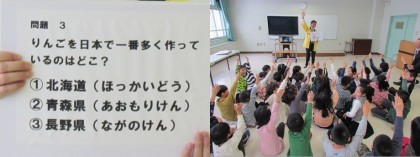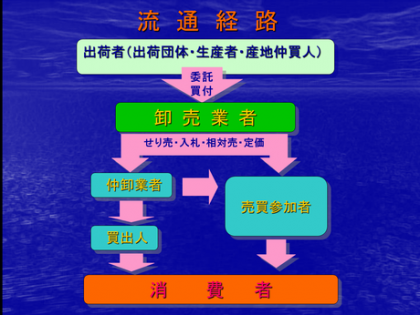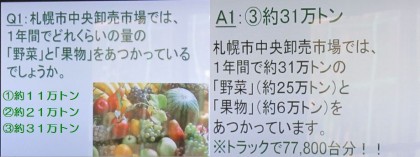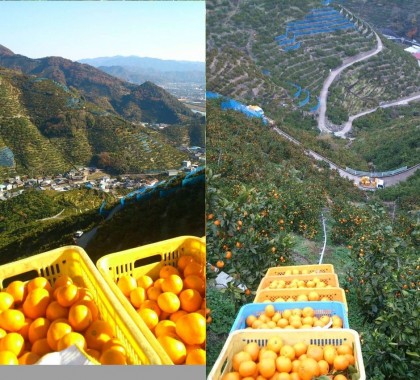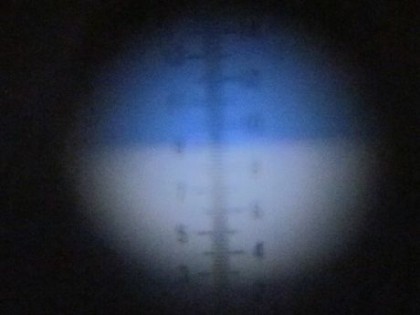10月25日(土)、当市場の青果部運営協議会主催の「市場で学ぶ・作る・食べるやさい・くだもの料理教室」が開催されました。今回は40名が参加しました。
なお、この料理教室は、生活習慣病の予防に効果的とされる野菜や果物を、普段の食生活に取り入れていただくことを目的として開催されています。

当市場では大根、白菜、キャベツが大量に入荷されている今日この頃。料理教室の最終回はそんな季節にふさわしく「漬物教室」です。
本日の講師は、第9回料理教室の講師もしていただいた、「お料理サロンうららか」主宰の坂下美樹先生です。
参加者の方々から先生に対して、「独身なの?30代なの?」と聞かれてちょっと嬉しくなったという坂下先生。
確かに漬物教室の先生には見えなかったかもしれないですね。(ご年齢のほうは、ヒ・ミ・ツ)
ちなみにテレビで坂下先生出演のコマーシャルを見た時は、「本当に出てる~!」とビックリしてしまいました。
さて、今日はどのような漬物を教えていただけるかというと、タルで漬けるような本格的ものではなく、初めての方でも簡単に作れる漬物ということ。
それでは料理教室の模様をご紹介します。なお、レシピもご参照ください。
「1.大根の葡萄漬け」

二十年ほど前にある料理教室の生徒さんから教わったものです。自分で塩分のパーセントや使うブドウなどをアレンジして、現在のレシピとなったようです。
本来は生の大根でやるのですが、干し大根でも大丈夫とのこと。ただし、干し大根には皮がついていて、色がなかなか浸透しづらいのですが、皮にはうま味や栄養分も含んでいるので、皮を薄くむくか、そのままでもいいとのことです。
生の大根で作ると、サラダ感覚で食べることができますが、つけ汁が余るので少しもったいないです。

大根は袋に入りやすいように、縦に割ってください。
レシピでは、ブドウはスチューベンとなっていますが、キャンベルだと糖度が高く、色がつきやすいです。スチューベンだとあっさり目にできあがるとのこと。
ミキサーにはブドウの房をそのままかける方法もありますが、時間がかかるので房を外しています。ミキサーにかけた場合、すぐに洗わないと色が取れなくなる可能性があるので注意です。

左側写真・・・大根の入った袋にこしたブドウ、塩、酢、ざらめ、赤トウガラシを入れます。塩は大根1本の重さの3%です。ご自分で野菜の重さを量ってから塩分を出すというのが漬物の基本中の基本。また、酢を入れるとブドウのアントシア二ンという成分がきれいに発色します。
右側写真・・・大根とつけ汁を入れた袋から空気を抜いて、冷蔵庫に入れます。このまま冷蔵庫に入れて、5日目くらいで色が付いていい感じになるとのこと。生の大根だと漬け込んでから1、2週間くらい持ちます。
「2.白菜の即席キムチ」


左側写真・・・白菜を葉と芯に分けて、それぞれ繊維に沿って太目の千切りにします。芯は塩をまぶしてから葉に混ぜます。ちなみに芯は一番おいしい部分です。鍋には薄く切って入れるか、そのまま入れてダシにしてもいいですよ。
右側写真・・・白菜の上に重石(おもし)を載せて、しんなりさせましょう。重石がなければ、ボウルに水を入れたものでも大丈夫です。ニンジンも千切りにしますが、白菜とニンジンは最後に水気をしっかり絞っておきましょう。

左側写真・・・リンゴのすりおろしは皮はむかなくてもいいです。色が茶色くなっても、調味料が入るので大丈夫とのこと。
右側写真・・・計7種類のものを混ぜ合わせ、それに白菜とニンジンを加えてよくもみ込むと完成です。漬けている時間は白菜の芯を塩漬けしているときだけです。
・韓国産の粉唐辛子は、粗挽きだとちょっと辛いので、細引き、中引きがいいとのこと。一味や七味でもちょっと辛いです。
・ナンプラーは発酵していないのに、即席で発酵の味を出せる調味料です。チャーハンなどに少し入れてもおいしいですよ。
・半ずり白ごまは市販の煎りごまを少し煎りなおすと、香りがもっと良くなります。
・ゆずの皮は白い部分が残らないように切ります。
先生「お砂糖とお塩は間違えないように気をつけてください。。。って、私そう言ってて、今どっちがどっちかわからなくなっているんですよ(笑)」
「3.福神漬け」

先生によると、北海道や一部の地域では「ふくしんづけ」と言うようなんですが、そのほかの地域では「ふくじんづけ」と言われ、その理由はわからないとのこと。
今回の福神漬けは、冷蔵庫の残り物などを使うイメージでレシピを作りました。
ちなみにこの料理は、「森崎博之のあぐり王国北海道」と言うテレビ番組でタレントの森崎さんにも作ったのですが、その後、森崎さんとお会いした時に、「うちで何回も作りました!」と言ってくださったようです。

写真左側・・・れんこん、にんじん、大根は銀杏ぎりで厚さ2㎜くらい、みょうがは小口切り、きゅうりは縦に半分に切ってから1~2㎜の薄切り、しょうがは繊維に沿って千切りです。しいたけはしめじでも代用可能で小さ目に切ります 。。。写真が見づらくて申し訳ありません。
写真右側・・・なすは半月切り
れんこんのアクが気になる場合は、酢水に入れてアクを抜きます。
なすは塩につけたり、水につけてアクを抜きます。ちなみになすは焼いても油でアクが抜けます。

切り終えた野菜をボールに入れて、野菜の重さの2%の塩を入れます。この時の塩は、食卓で使う塩では塩味が強いので、ミネラル成分が入った自然の塩のほうがいいです。
塩をかけて水気が出てきてから、揉むのがベストです。
醤油、水、酢、みりん、酒、砂糖を鍋に入れて、さっと煮立てます。この時、ゆずのしぼり汁を入れるとさっぱり仕上がります。
野菜の水気が取れたら、右下の写真ぐらいまで軽く煮立てます。
皆さんの想像する赤い福神漬けとはちょっと違うかもしれませんが完成です。これもサラダのような感じで、ゴマを入れても香ばしくておいしいですよ。

先生も昔からお母様に習って、漬物をよく作っていたとのこと。この時期になると大根を洗うことが多く、水が冷たくて本当に嫌だった記憶があるそうです。そういう記憶って、不思議と覚えているものですね。
ちなみに先生の漬物を試食したところ、サラダ感覚といいつつも、ご飯のおかずにどれか一品あれば大丈夫という正真正銘「漬物」でした。
「1.大根の葡萄漬け」は本当に漬物?というくらいブドウの風味が効いているのですが、これはこれでご飯がとても進みます!
先生の漬物のレシピは、長い時間漬けるなどの手間を極力省いたものですので、皆さんも気軽に漬物を楽しんでみてはどうでしょうか?